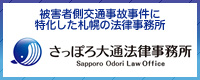裁判所が接骨院・整骨院の施術費を賠償金として認める基準
2015/04/16
片岡武裁判官の赤本講演録「東洋医学による施術費」
片岡武裁判官は、赤本講演録において、接骨院・整骨院の施術費について、医師の指示がなくとも事故との因果関係を肯定すべき場合があることを明言して、以下のとおり、要件を挙げられています。医師の指示の有無
原則として、施術を受けるにつき医師の指示必要。ただし、医師の指示なくとも、施術を認めるべき場合あり。
【理由】
1 柔道整復師には医師の指示がなくとも施術ができる業務範囲が存在する。
2 西洋医学的治療より効果的な臨床例あり
3 整形外科の治療の代替機能あり
4 施術の利便性(かかり易さ)
5 地域の実情等
賠償金として認められる要件
1 施術の必要性施術を行うことが必要な身体状況にあること
2 施術の有効性
施術を行った結果、具体的な症状緩和の効果があること
3 施術内容が合理的
施術が受傷内容と症状に照らして、過剰・濃厚でないこと。
4 施術期間の相当性
受傷の内容(事故の大きさ)、治療経過、疼痛の内容等から期間が相当か。
「初療の日から6ヶ月を一応の目安としたらどうか」
「施術の必要性の立証ができれば、これを超える期間についての施術を認めるべきでしょう」
5 施術費の相当性
報酬金額が社会一般の基準と比較して妥当か。
「労災料金の1.5~2倍を上限の目安としたらどうか」
医師の指示なく肯定した裁判例
裁判例を分析すると、施術費について、全額認めるパターン、割合的に一部を認めるパターン、慰謝料で考慮するパターンがあることが分かります。全額認めるパターン
| 大阪地裁平成22年8月26日判決 |
|
被告らは、原告の通院期間の必要性及び相当性について特によしやま鍼灸整骨院での施術の必要性及び相当性について疑義を呈するものの、原告本人尋問の結果によれば、原告の症状は、日を追うごとに回復し、現在本件事故前と同じく調理師として稼働している事実が認められることからすれば、原告が、症状固定日までに受けた治療ないし施術は効果が認められたものというべきであるから、上記50万2755円は、本件事故と相当因果関係が認められる損害というべきである。 |
| 東京地裁平成26年2月28日判決 |
|
原告は、平成21年6月15日からうえだ整骨院へ通院するようになった。うえだ整骨院では、頸部捻挫との負傷名の下、施術を受けたが、寛解と増悪を繰り返す状態であった。 なお、原告は、杏林大学医学部附属病院に提出した書面において、うえだ整骨院でマッサージを受けると痛みや頭痛が軽減し、うえだ整骨院の施術が最も効果があるので、続けているとしている。 うえだ整骨院への通院については、医師の指示はないが、前記1で認定した事実経過によれば、原告の症状緩和に効果的であったことが認められるから、本件事故と相当因果関係を認めるのが相当である。 |
7割、5割、3割と割合的に一部を認めるパターン
| 大阪地裁平成25年11月21日判決 |
|
接骨院の施術費 証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告X1は、本件傷害について施術を受けるために接骨院に通院し、施術費一一八万一四八〇円(原告保険会社との協定後の額)を要したことが認められる。 以上の事情を総合考慮すると、上記施術費の7割をもって、相当性を認める。 |
| 東京地裁平成25年12月27日判決 |
|
上記症状固定に至るまでの施術回数の2分の1の限度で、有効性・合理性を認めるのが相当である。 |
| 東京地裁平成26年7月11日判決 |
|
接骨院等での施術費について検討するに、前記認定のとおり、原告は主に上記接骨院等での施術を主に受けており、その結果徐々に症状が改善していったと認められるから、原告に対する施術の必要性自体を否定することはできない。 もっとも原告は、A医師から接骨院等での施術を指示されておらず、むしろ複数回にわたって整形外科の受診を勧められながら、平成22年7月27日から平成23年12月21日までの513日間という長期間において、合計256日、平均して約2日に1日を超える割合で接骨院等での施術を受けていたものであり、原告の傷害の内容及び程度に照らすと、これらの施術の全てが、傷害の治癒という目的に照らして必要な施術であったと認めることはできず、本件事故と相当因果関係のある施術費としては、各接骨院等での施術費の2分の1である、49万0812円に限って、本件事故と相当因果関係のある損害と認める。 |
| 東京地裁平成25年12月25日判決 |
|
整骨院の施術料については、施術の必要性、有効性及び相当性に鑑み、平成24年3月から同年9月までの施術料の約3割に相当する30万円の限度で本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。 |
| 大阪地裁平成13年8月28日判決 |
|
症状固定までの間における中西接骨院の120万7310円については、医師の明確な指示を受けたことの証明はないが、ある程度の痛みを緩和する効果はあったものと認められるので、原告の治療経過に鑑みて、その内の30万円をもって本件事故と相当因果関係のある損害と認める。 |
慰謝料で考慮するパターン
| 東京地裁平成14年2月22日判決 |
|
前示のとおり、やはき整骨院での施術が有効であったことは認められるが、その施術を行うことの必要性、合理性、相当性が認められない以上、同施術に要した費用を損害として加害者に負担させるのは相当ではない。 もっとも、前示のとおり、施術が原告の症状に有効であったこと、この施術期間中整形外科の治療費の支出がなかったこと(原告が医師による治療を選択せず、これを受ける機会が少なかったため、算定されるべき治療費に係る損害額も少なくなる。)を考慮すると、施術費を損害として計上せずに被害者たる原告の自己負担としてしまうことは、必ずしも、公平の観点から見て相当とはいい難い。 当裁判所は、原告が、施術費を自己負担をしてでも施術を受けて軽快させたいと思う程度の症状に苛まれていた、との観点から、これを、後述する感謝料の加算事情として積極的に評価するのが相当であると考える。これに対し、施術費中の幾らかを損害額として割合的に認定する考え方もあり得るが、そのような算定をするための合理的な基礎資料を収集、整理し、提出することは一般に容易ではなく、本件でもそれは十分でないため、割合数値を設定することは困難である。そこで、本件では、民事訴訟法248条によって、あえて施術費の費目で損害額を認定するよりは、むしろ、算定困難な損害額の算定として有用な慰謝料の費目で計上するのが合理的かつ相当であると判断した。 |
整骨院への通院が認められる期間の目安
2015/03/25
交通事故の被害者の方が整骨院ないし接骨院に通院される際、通院期間が問題となることが少なくありません。
これについて、平成14年11月2日の講演で、裁判官が整骨院ないし接骨院への通院期間について、一つの考え方を明示しています。
「施術期間は、初療の日から6ヶ月を一応の目安としたらどうでしょうか」として、6ヶ月という数字を提示されています。
さらに、「施術の必要性の立証ができれば、これを超える期間についての施術を認めるべきでしょう」とされています。
金額についても、言及しており、労災の1.5~2倍を上限の目安としてはどうかと提言されています。
通院期間の相当性については、事故の大きさにも影響されると考えられますが、裁判官が6ヶ月という具体的な期間を提示している意味は大きいです。
特に、東京地裁民事27部という交通専門部の裁判官による発言ですから尚更です。
この講演の記録は、交通事故に携わる実務家が必ず目にしている、いわゆる赤本に講演録として掲載されていますので、裁判官、弁護士はもとより保険会社の担当者も当然目にしているはずです。
そういう意味では、保険会社の担当者からの短期間での打ち切りに対して、反論する有力な材料といえます。
これについて、平成14年11月2日の講演で、裁判官が整骨院ないし接骨院への通院期間について、一つの考え方を明示しています。
「施術期間は、初療の日から6ヶ月を一応の目安としたらどうでしょうか」として、6ヶ月という数字を提示されています。
さらに、「施術の必要性の立証ができれば、これを超える期間についての施術を認めるべきでしょう」とされています。
金額についても、言及しており、労災の1.5~2倍を上限の目安としてはどうかと提言されています。
通院期間の相当性については、事故の大きさにも影響されると考えられますが、裁判官が6ヶ月という具体的な期間を提示している意味は大きいです。
特に、東京地裁民事27部という交通専門部の裁判官による発言ですから尚更です。
この講演の記録は、交通事故に携わる実務家が必ず目にしている、いわゆる赤本に講演録として掲載されていますので、裁判官、弁護士はもとより保険会社の担当者も当然目にしているはずです。
そういう意味では、保険会社の担当者からの短期間での打ち切りに対して、反論する有力な材料といえます。
施術の必要性・効果の立証
2015/03/19
交通事故における整骨院の施術費が問題となった事案において、注意を要する裁判例の紹介です。
大分地裁平成25年9月20日判決は、加害者の保険会社が治療中に一旦、施術費を立て替えて支払っていたにもかかわらず、最終的に、事故との相当因果関係がないとして、施術費の賠償を否定しました。
本判決は、被害者の方が、信号待ち停車中に後ろから追突され、頚椎捻挫等で、約7ヶ月間通院された事案です。
被害者の方は、平成23年1月~7月まで、加害者が加入していたF共済担当者の了解を得て、D整骨院に通院して、6月分までの45万4420円は、一旦、F共済が負担していました。
ところが、訴訟提起後、加害者の弁護士が、一旦、F共済にて、支払い済みのD整骨院の施術費45万4420円について、事故と因果関係がないと主張してきたものです。
被害者側の弁護士も、禁反言に反し、信義則上許されない等と反論をしています。
大分地方裁判所は、最終的に
①医師の指示がない
②施術の効果を裏付ける医学的根拠がない
等として、D整骨院の施術費の事故との因果関係を否定しました。
このように、治療段階で、相手方保険会社から支払がなされていても、裁判に至った場合、事故との相当因果関係が否定されることがあります。
レアな裁判例だとは思われますが、整骨院の施術費が裁判で問題となった場合には、施術録の記載などから、施術の必要性・効果を丁寧に立証する必要があります。
注意が必要な裁判例といえます。
ちなみに、この地裁の判断は、福岡高裁でも維持されています。
大分地裁平成25年9月20日判決は、加害者の保険会社が治療中に一旦、施術費を立て替えて支払っていたにもかかわらず、最終的に、事故との相当因果関係がないとして、施術費の賠償を否定しました。
本判決は、被害者の方が、信号待ち停車中に後ろから追突され、頚椎捻挫等で、約7ヶ月間通院された事案です。
被害者の方は、平成23年1月~7月まで、加害者が加入していたF共済担当者の了解を得て、D整骨院に通院して、6月分までの45万4420円は、一旦、F共済が負担していました。
ところが、訴訟提起後、加害者の弁護士が、一旦、F共済にて、支払い済みのD整骨院の施術費45万4420円について、事故と因果関係がないと主張してきたものです。
被害者側の弁護士も、禁反言に反し、信義則上許されない等と反論をしています。
大分地方裁判所は、最終的に
①医師の指示がない
②施術の効果を裏付ける医学的根拠がない
等として、D整骨院の施術費の事故との因果関係を否定しました。
このように、治療段階で、相手方保険会社から支払がなされていても、裁判に至った場合、事故との相当因果関係が否定されることがあります。
レアな裁判例だとは思われますが、整骨院の施術費が裁判で問題となった場合には、施術録の記載などから、施術の必要性・効果を丁寧に立証する必要があります。
注意が必要な裁判例といえます。
ちなみに、この地裁の判断は、福岡高裁でも維持されています。
Copyright (C) 桝田・丹羽法律事務所 All Rights Reserved.

 当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。
当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。